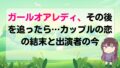「え、なんかこのCM…不気味?」
「ピザのはずなのに、全然おいしそうに見えない…」
最近SNSで、そんな声を見かけたことはありませんか?
2025年夏、ドミノピザが公開した新CMが話題を集めました。
なぜかというと、出演者から映像のすべてが“AIによって生成された”完全AI広告だったからです。
一見すると普通のCMに見えますが、見れば見るほど「なんか変…」という違和感が湧いてきます。
この記事では、その違和感の正体と、AI広告のこれからについて深掘りしていきます。
ドミノのあのCM、やっぱAI?
CMを見た視聴者の多くが、「これってAIなのでは?」と驚きの声を上げました。
X(旧Twitter)では、こんな書き込みが目立ちました:
- 「ドミノのCM、あれCGじゃない?なんか変なんだけど…」
- 「見た瞬間に“AIっぽい!”って思った。笑顔が怖い」
- 「動きがカクカクしてるし、人間味がゼロ。不自然すぎる」
あまりにも不自然な表情や所作に、視聴者が「人間ではない何か」を直感的に察知していたことがわかります。
そして、後に報じられた情報によって、CMは完全にAIによる生成で作られた映像であることが明らかになりました。
AIで作られた登場人物、CG処理された食事風景、そしてスムーズすぎるカメラワーク。
これらすべてが、実写ではない“AIの作品”だったのです。
視聴者の中には、「ドミノピザの攻めた姿勢すごい」「こんなCM初めて見た」と技術に感心する声もありましたが、
「気持ち悪くてチャンネル変えた」「逆に食欲なくす」といった感情的な拒否反応も多数見受けられました。
つまり、“ドミノピザのCM=AI”という事実そのものが、多くの人に驚きと戸惑いを与えたのです。
このCMが「なんか不気味」と言われるワケ
ドミノピザが公開したAI CMは、バーチャル俳優を使って制作されました。
一見、家族団らんでピザを囲む映像に見えるのですが、よく見ると表情や動作がどこかぎこちない。
視線が合わない、笑顔が固い、動きが機械的——そんな細かな違和感が積み重なり、「不気味」という印象につながってしまったのです。
ドミノピザの生成AIで作ったCMが怖過ぎる pic.twitter.com/Gcy6Nk55cM
— tsuperan (@tsuperan) August 11, 2025
お盆シーズンに合わせて、家族で楽しめるお得なキャンペーンを紹介する内容です。
明るい音楽とともに、映像としては、ピザやサイドメニューを囲んで家族が楽しく過ごしている様子が描かれ、夏らしい賑やかな雰囲気でまとめられています。
ドミノのAIっぽいCMは?
じつはこのCMはAIによってすべて合成されており、俳優は存在しません。
リアルな家庭のシーンを模した映像ですが、人間の視覚と感覚は、微細な不自然さをすぐに察知してしまいます。
みんなの本音
X(旧Twitter)やYouTubeでは、「マネキンみたい」「夢に出てきそう」「ピザがまずそう」といった声が続出。
反応はさまざまでしたが、共通していたのは“違和感を感じた”という点でした。
たとえば、以下のような声がネットで目立ちました:
- 「パッと見は普通だけど、目の奥に何かを感じる。不気味すぎる」
- 「あの笑顔、見れば見るほどゾッとする」
- 「最初は気にならなかったけど、何回も見てたら怖くなってきた」
- 「人間じゃないと分かってからもう直視できない」
- 「食べ物のCMであんな無機質な映像は逆効果だと思う」
ドミノピザの新CMはAIかな?
マネキンがピザ食ってるような不気味さで、全く食欲をそそられなかった😯
生きてる人間が美味しそうに食べるCMって大事だったんだな〜— らむぼ (@spoteto) August 5, 2025
こうした反応を見ると、視聴者の多くが「自分だけが気にしすぎかも…?」と思いながらも、
何か言葉にできない違和感を共有していたことがわかります。

良くも悪くも、AI広告が世間に与えるインパクトは想像以上でした。
違和感の正体は“人の心理”
視聴者が感じたその「違和感」には、不気味の谷現象が大きく関係しています。
「不気味の谷」って何?
いわゆる「不気味の谷」とは、人間に似て非なる存在に対して、人間が無意識に違和感や不快感を覚える心理現象のこと。
1970年、ロボット工学者の森政弘氏によって提唱された概念で、ロボットやCGキャラクター、AI映像などに応用されてきました。
たとえば、ロボットの顔がリアルになればなるほど、ちょっとした違和感が逆に目立つようになり、「気持ち悪い」「怖い」と感じてしまう。
これがまさに「不気味の谷」です。

人間に“そっくり”だけど完璧ではないAI表現が、脳に警戒信号を送ってしまうのです。
目線や表情、質感がズレて見える理由
たとえば、笑顔が目元と口元で一致していない、まばたきが不自然、皮膚の質感が妙に滑らかすぎる——こういった微細なズレが積もることで、「怖い」と感じてしまいます。
なんでお腹が減らない?AI映像の壁
CMを見て「ピザがまずそうに見える」と感じた人は少なくありません。
ドミノピザのCMが
AIっぽくて気持ち悪い
食欲なくす#ドミノピザ@dominos_JP pic.twitter.com/T9fYvOOIov— NOKOSUKE24 (@NOKOSUKE) August 17, 2025
なぜ“おいしさ”が足りない?
本物のピザには、チーズの不均一な溶け具合や、アツアツの湯気など、感覚を刺激する要素が詰まっています。
しかし、AI映像ではそれが再現しきれていないのです。

質感や温度の「曖昧さ」が、食欲をかき立てるどころか冷めさせてしまう。
「おいしそう」は“温かみ”が決め手
視覚情報だけでなく、共感や想像力を引き出す“温かさ”こそが、食品広告のカギなのです。
私自身、CMを初めて見たとき「うわ、なんかおいしそうに見えない…」と感じました。
目線が合っていなかったり、笑顔が無理に作られている感じがして、「これ本当に人間?」と疑ってしまいました。
あえて不気味?その狙いは
一部では「これはわざと不気味にして拡散を狙ったのでは?」という見方もあります。
バズ狙いは本当?
バズ狙いで「あえて炎上気味に仕上げた」のでは?という推測が飛び交いました。
実際、「不気味だけどクセになる」とリピート視聴する人も多く、拡散効果は絶大だったと言えます。
バズ優先かブランド優先か
確かに、CMは多くの人の注目を集め、「ドミノピザ=話題性のある企業」という印象を与えたかもしれません。
SNSで拡散され、メディアでも取り上げられ、「あのCM見た?」という会話が生まれること自体は、マーケティングとしては大きな成功とも言えます。
しかし一方で、「なんか不気味なCMの会社」「もう頼む気がしない」と感じた人もいたはずです。
話題性は得られる一方で、「不気味なピザの会社」という印象が残るリスクも否定できません。
このような印象が強く根付いてしまうと、短期的な注目を集めたとしても、
長期的に見て「安心して選ばれるブランド」にはつながらない可能性があります。
特に食品業界では、「見た目が美味しそう」「清潔感がある」「信頼できる」といった要素が購買の決め手になります。
どれだけ技術的にすごいことをやっていても、「怖い」「気持ち悪い」というイメージがついてしまえば、日常的な購買行動にはつながりません。
インパクトの強さと、ブランドの信頼感は時に相反する。

それをどうバランスさせるかが、今後のAI広告戦略における大きな課題と言えるでしょう。
AI広告は人の“感覚”を越えられる?
AIには効率性やコスト削減など多くの利点があります。
しかし広告においては、共感こそが重要です。
AI映像の可能性と課題
AI技術は年々進化し、今では非常にリアルな人物や映像を生成できるようになりました。
映像の滑らかさ、光の反射、表情の変化——技術的には驚くほど精度が高まっています。
しかし、「人間らしさ」「温かみ」「違和感のなさ」をすべて同時に再現することは、まだ難しいのが現状です。
ちょっとした目の動き、呼吸のリズム、肌の微妙な動きなど、人間が無意識に読み取っている情報を、AIは完全には再現できません。

だからこそ、リアルに“見える”けれど“感じられない”というズレが生まれ、視聴者の中に違和感が残るのですね。
広告に必要なのは“リアル”より“共感”
広告の本質は、製品やサービスの情報を届けるだけではありません。
見る人の心に「これいいな」「使ってみたい」と思わせる“感情の動き”を作ることが大切なのです。
いくら映像が美しくても、そこに“人間らしさ”や“温もり”が感じられなければ、心には響きません。
視聴者の心を動かすのは、データや映像の精密さではなく、
共感できるストーリー、感情に触れる瞬間、そして“誰かのリアルな体験”です。

今後のAI広告に求められるのは、技術の追求だけでなく、「どうすれば人の心を動かせるか」という視点です。
まとめ:AIと人のほどよい距離感
今回のCMは、AI広告の可能性と限界を同時に示した象徴的なケースでした。
AI技術は進化し続けますが、人間の“感覚”はそれを超える判断基準を持っています。
便利で斬新であると同時に、「共感できるかどうか」が、今後の広告を決める大きな要素になるでしょう。
これからの広告は「違和感のなさ」だけでなく、「共鳴できる体験」が求められます。
AIと人間がうまく共存する未来を、私たち自身も見極めていく時代が始まっているのかもしれません。