「横山温大選手って、どこの小学校や中学校出身なんだろう?」――そんな疑問を持ったことはありませんか?
この記事では、岐阜県各務原市出身の横山温大選手について、小学校・中学校時代のエピソードから、高校での活躍、そしてプレースタイルまで詳しく解説します。
成長の軌跡をたどれば、彼の魅力がもっと深く見えてきます。
横山温大選手とは?プロフィールと経歴概要
横山温大(よこやま・はると)選手――名前だけでもスポーツ選手らしい響きですよね。
2007年7月17日生まれ、岐阜県各務原市の出身です。ポジションは内野手。右投げ左打ちで、守備の安定感と俊足が持ち味です。
私が初めて彼を見たのは、高校野球の試合中継でした。
打球が内野を抜ける…と思った瞬間、信じられない速さでボールに追いつき、スッと一塁へ正確に送球。あの一瞬で「この選手はただ者じゃない」と確信しました。
野球を始めたのは小学3年生。
地元の「緑陽スポーツ少年団」に入ってからは、もう野球漬けの日々だったそうです。
横山温大選手の出身小学校はどこ?
横山選手の小学校名は公式には公表されていませんが、小学3年生から所属していた緑陽スポーツ少年団の活動拠点が各務原市立緑陽小学校やその周辺であることから、この近隣の学校に通っていた可能性が高いと考えられます。
少年野球チーム「緑陽スポーツ少年団」での活躍
少年団時代の横山選手は、とにかく守備がうまい子でした。
ある大会で、相手打者が放った一二塁間へのゴロを、信じられない速さで追いつき、一塁へ送球。塁審が思わず「アウト!」と声を張り上げると、ベンチも観客席も拍手喝采。
小学生ながら落ち着き払った表情で次の守備位置につく姿に、チームメイトも頼もしさを感じていたそうです。
練習ではいつも最後までグラウンドに残り、ノックを何度も受けていた姿が印象的。
あの頃の泥だらけのユニフォームが、今の横山選手の基礎を作ったのだと思います。
横山温大選手の中学校時代
横山温大選手は、中学校は各務原市立緑陽中学校。
部活動に加えて、硬式野球クラブ愛知江南ボーイズでもプレーし、よりハイレベルな環境で腕を磨きました。
愛知江南ボーイズで硬式野球に挑戦
中学時代のある試合では、三遊間を抜けそうな打球をダイビングキャッチし、そのまま二塁へ送球してダブルプレーを完成。
観客席からは「今のプレー、高校生でも難しいぞ!」という声も上がるほどでした。
愛知江南ボーイズでは、守備だけでなく打撃面でも成長。
チャンスで回ってきた打席では、力みに頼らず鋭いライナーを外野へ運び、勝負強さを発揮しました。
仲間からも「ここで打ってくれる」という信頼が厚く、試合後の握手にはいつも笑顔があふれていました。
練習中も妥協せず、守備位置の一歩目を何度も確認する姿や、打撃フォームを微調整する姿は、周囲の中学生とは一線を画していました。
この積み重ねが、高校での活躍に直結していきます。
高校進学と甲子園での躍動
中学卒業後は県岐阜商業高校へ。
県内屈指の名門で、歴代多くのプロ選手を輩出しています。
1年生からベンチ入りし、3年春には背番号17で甲子園の舞台へ。
あの広い甲子園のグラウンドでも、横山選手の守備は映えました。
県大会の準々決勝では、三遊間への痛烈な打球を横っ飛びでキャッチし、体勢を崩さずに一塁へ送球。
このビッグプレーが試合の流れを変え、スタンドを沸かせました。
横山温大選手のプレースタイルと魅力
横山選手の一番の持ち味は、やはり守備範囲の広さと初動の速さです。
打球が放たれた瞬間、そのコースを正確に読み取り、迷いのない一歩目でポジションへと走り込みます。

まるで打球の未来を予知しているかのような動きは、少年野球時代から積み重ねてきた観察力と経験の賜物でしょう。
右手にグラブを装着し、捕球から送球までの動作を一瞬でこなす独特のプレースタイルが光ります。
球際の強さも際立っています。
強烈なライナーやイレギュラーなバウンドにも、体勢を崩すことなくスムーズに対応。
捕球から送球までの一連の動作が無駄なく流れ、鋭くも正確な送球が一塁手のミットに吸い込まれます。
走塁面では俊足を生かし、打球判断も的確。
次の塁を迷わず狙う積極性は、相手守備陣にプレッシャーを与えます。
バッティングでも、チーム状況に応じて小技から長打まで柔軟に対応できるのが魅力です。
背番号とその意味
背番号を手にするまでの道のり
横山温大選手が現在背負っているのは、岐阜県立岐阜商業高校の外野手を象徴する背番号「9」。この番号は、ただ与えられるものではなく、日々の練習態度や試合での実績、そして監督からの信頼を勝ち取った選手だけが手にできる“特別な番号”です。
高校入学時は控え番号からのスタート。
中学時代に鍛えた守備力や俊足はあったものの、甲子園常連校の環境では通用しない場面も多く、横山選手はひたすら基礎練習と体力強化に取り組みました。
誰よりも声を出し、試合に出られない日も全力でチームを支える――その姿勢が評価され、3年春に背番号17でベンチ入り。
そして夏の大会を前に、監督はついに外野手の“主戦番号”である「9」を託しました。
背番号に込められた思い
横山選手にとって「9」はただの数字ではなく、責任と信頼の証です。
岐阜商業の「9番」は歴代の名外野手が背負い、甲子園で数々の名プレーを生んできた番号。
横山選手もその系譜に名を連ねることを意識し、「この番号を着る以上、チームの勝利に直結するプレーをする」と強い決意を胸に刻みました。
また、この番号は彼が生まれ持ったハンディキャップを乗り越えた証でもあります。
左手の指がなくても、努力と工夫でレギュラーの座を掴み取ったことを示す象徴であります。

同じ境遇の子どもたちに「夢は諦めなくていい」と伝えるメッセージにもなっています。
甲子園で「9番」を背負った瞬間
2025年夏の甲子園、初戦の相手は日大山形高校。
横山選手は背番号「9」を背に、広い甲子園の外野へと駆け出しました。
背中に感じる番号の重みと、スタンドからの大声援。
試合開始前、外野から内野方向を見渡した瞬間、「自分はこの舞台に立つためにやってきたんだ」と実感が込み上げたといいます。
五回にはライト前への同点タイムリーを放ち、ベンチの仲間たちが笑顔で迎え入れます。
七回、相手のライナー性の打球が右中間を襲うと、俊足で追いつき右手一本でキャッチ。
そのまま素早く握り替え、三塁へ矢のような送球を決め、タッチアップを試みたランナーをアウトにしました。
観客席からは大きなどよめきが起こり、実況も「9番、横山!見事な守備です!」と興奮気味に伝えました。

あの瞬間、背番号「9」はただの数字ではなく、“甲子園で仲間を救う守備の象徴”となったのです。
周囲が感じる背番号の重み
監督は「背番号は選手の覚悟を示す」と語り、チームメイトも「横山が9番を着ると外野が引き締まる」と口を揃えます。
甲子園での一挙手一投足が、仲間や観客、そして全国の野球ファンの心を動かしました。

横山温大選手にとって、この「9」は過去の努力と未来への挑戦、その両方を背負った誇りそのものなのです。
甲子園での活躍と感動
2025年の岐阜大会では打率.526を記録し、全国大会進出に大きく貢献。
甲子園初戦の日大山形戦でもマルチ安打を放ち、同点打で会場を沸かせました。
守備でも右手一本の送球でランナーを刺すなど、彼の存在感は試合を通して際立っていました。
試合後のインタビューで語った「どんなハンディキャップがあっても、全力で取り組めば夢は叶う」という言葉は、多くの人の胸に響きました。
横山温大の守備スタイルと特長は?
片手から繰り出す正確なスローイング
横山選手の守備でまず目を引くのは、右腕だけで放つ正確無比なスローです。
左手の指がないという生まれつきのハンディキャップを抱えながらも、片手一本で鋭い送球を可能にしています。

外野からホームへ一直線に伸びる“ワンハンドレーザー”は、甲子園の観客席からも思わず歓声が上がるほど。
この独自の送球フォームは、幼少期から何度も試行錯誤を繰り返し、グラブや握り替えの方法に工夫を凝らした努力の結晶です。
グラブの工夫と握り替えの練習
愛用のグラブは軽量でフィット感抜群。
捕球後は素早く外してボールを握り替え、そのまま送球する一連の流れを体に染み込ませています。
中学時代から何千、何万回と繰り返してきた動作は、今では横山選手の代名詞といえるほど自然でスムーズです。
俊足と広大な守備エリア
横山選手のもう一つの武器が、抜群の脚力とフィールド全体をカバーできる広さです。
打球が飛んだ瞬間、一歩目の反応が速く、他の外野手では届かないエリアにもスムーズに追いつきます。

まるで芝生の上を駆け抜けるスプリンターのようなスピード感で、守備範囲を最大限に広げています。
この走力とカバー力の高さは、中学時代から鍛えたフットワークと瞬発力の賜物であり、チームに大きな安心感をもたらします。
際どい打球をものにする勝負強さ
さらに特筆すべきは、ギリギリの場面でこそ発揮される球際の強さと瞬時の判断力です。
低いライナーやイレギュラーなバウンドにも迷わず飛び込み、確実にアウトへとつなげます。
この勝負どころでの集中力は、相手の打球傾向を素早く読み取る野球脳と、日々の厳しい練習によって培われた反射神経によるもの。
ピンチの場面でも動じない冷静さと、全力で食らいつく姿勢が、観客を熱狂させる理由です。
際どい打球も逃さない対応力
速いライナーや予測不能なイレギュラーバウンドにも、一切慌てることなく落ち着いて処理します。
相手打者の打球傾向やスイングの癖を一瞬で見抜き、瞬時に最適な守備位置へと移動できるのも大きな武器。
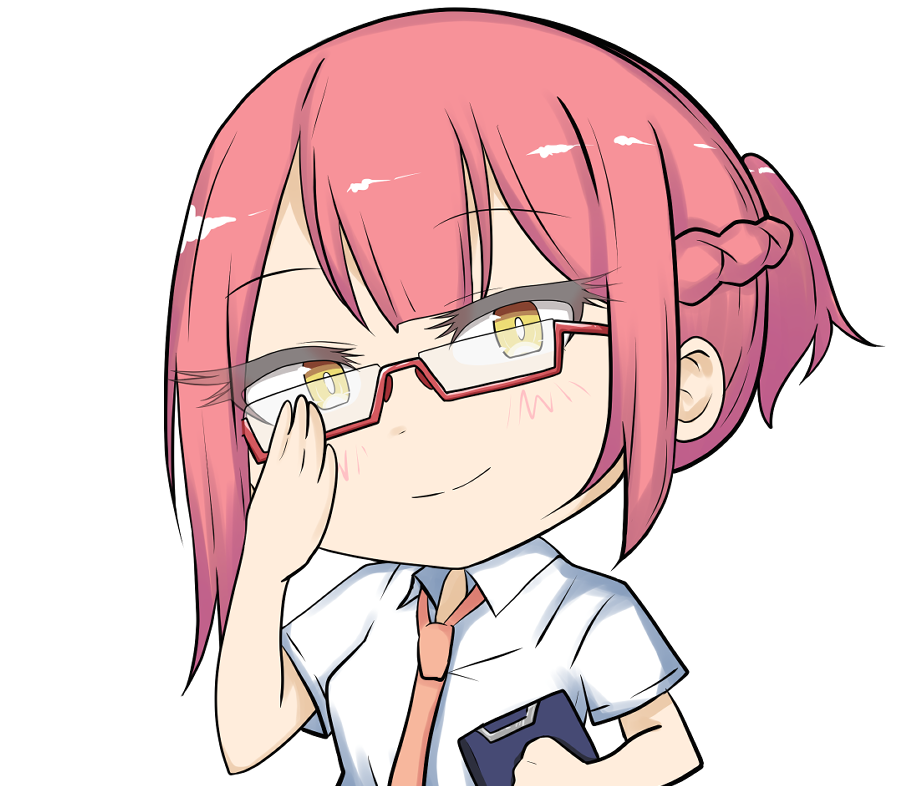
その的確な判断力と鋭い一歩目の動きは、長年積み重ねてきた練習量と試合経験の賜物であり、まさに努力の証です。
家族の支えと幼少期のエピソード
家族構成と兄姉の影響
両親と兄、姉の5人家族で育ちました。
兄は投手、姉は外野手として野球をしており、その影響で横山選手も小学3年で野球を始めます。
特に兄からは守備やバッティングの基礎を教わり、姉からは外野手としての心構えを学びました。
家族の励まし
左手のハンディキャップを理由に諦めることは一度も許されなかったそうです。
母は栄養バランスの取れた食事を用意し、父は練習相手としてグラウンドに立ち続けました。
横山温大選手は、単なる野球の上手い高校生ではありません。
生まれつきのハンディキャップを抱えながらも、自分の可能性を信じ、工夫と努力でそれを“武器”に変えてきた人です。
家族や地域の温かい支え、名門校での厳しい練習、そして甲子園での経験が、彼をさらに強く、魅力的な選手へと成長させました。

家族全員が“横山温大”というプロジェクトのチームメイトだったのです。
地域や仲間の応援
「江南ボーイズ」時代も、指導者や仲間が横山選手の特性に合わせた練習環境を整えてくれました。
地域全体が彼の成長を応援していたと言っても過言ではありません。
まとめ:小学校から積み重ねた努力と、これからの未来へ
泥だらけになりながらも一心にボールを追いかけていた小学生の頃。放課後、夕日が沈むグラウンドで、最後までノックを受け続けた日々。
中学生になると、練習環境も仲間も一気にレベルアップ。硬式野球の速い打球にも果敢に飛び込み、時にはダブルプレーを奪ってスタンドを沸かせました。
高校では甲子園の大舞台にも立ち、その広いフィールドでも落ち着いて守備をこなし、チームの勝利に貢献。その姿は、少年団時代から積み重ねてきた努力の証でした。
これまでの成長物語を知れば知るほど、これからの活躍に期待せずにはいられません。数年後、「あの横山選手がプロで活躍している!」と胸を張って言える日を楽しみにしています。

これから先、どの舞台に立っても、彼はきっと“挑戦する姿勢”で観る者を魅了し続けるでしょう。



コメント